【賃貸オーナー必見!】中古物件リノベーションの減価償却と耐用年数とは?

近年、既存の住まいを活用したり、中古住宅を購入して、賃貸経営を行う人が増えています。
そして、物件の価値を高めて入居者を集めるために、リノベーションを行うことが一般的ですが、リノベーション費用は経費として計上できることを知らない方も多いのではないでしょうか?
また、、リノベーション費用を経費計上する際に「減価償却」と「耐用年数」の2つの用語は理解しておかなければなりません。
そこで今回は、賃貸経営をしているオーナーの方に向けて、減価償却と耐用年数の意味について詳しく解説していきます。
物件オーナーは知っておきたい重要な2つの用語

物件を所有していて、他の人に貸し出しているオーナーであれば必ず知っておきたい2つの用語があります。
その用語とは、「減価償却」と「耐用年数」です。
まずは、この2つの用語について詳しく解説します。
減価償却とは?
一般的な事業における経費は発生した月に計上を行いますが、物件の購入費用のように資産に関する経費は一括で計上するのではなく、価値の減少に合わせて年数をかけて経費計上していきます。
そして、このような経費計上の仕組みを減価償却と言います。
また、資産の購入費用だけでなく、建物の修繕費用や新たな価値を生み出すリノベーションにかかった費用も減価償却のルールに則って経費計上しなければなりません。
会計処理の手間はかかってしまいますが、高額な支出も全て経費として計上できることが最大のメリットです。
耐用年数とは?
耐用年数とは、固定資産を妥当な用途用法で使用した場合に、役割を果たし続けられる期間のことです。
耐用年数は減価償却費を計算するために必要な値のため、中古物件を所有しているオーナーは必ず知っておいた方が良いでしょう。
取得した固定資産は年数の経過とともに価値が無くなり、耐用年数が0年になると帳簿上は価値がないとみなされます。
ただし、耐用年数が0年だからといって、物件自体が寿命を迎えているとは限らず、適切なリノベーションやリフォームを行うことで、寿命を伸ばすことが可能です。
そして、リノベーションした箇所や新たに設置した設備にはそれぞれ耐用年数が設定され、耐用年数を用いた減価償却により経費計上します。
中古物件リノベーションの減価償却で押さえておきたい注意点
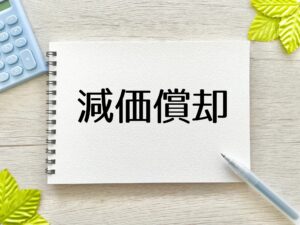
ここからは中古物件リノベーションの減価償却で押さえておきたい注意点について3つ紹介します。
資本的支出と修繕費の違いを理解しておく
リノベーション費用が減価償却の対象となるか判断するには、「資本的支出」と「修繕費」の2つの用語を理解しておく必要があります。
資本的支出と修繕費はどちらも固定資産の修繕または改良のために支出した金額とされていますが、修繕を行ったことで固定資産の価値が高まった場合は資本的支出とみなされます。
ただし、資本的支出と修繕費を分ける正確な基準はないため、以下の施工例を参考にしてください。
【資本的支出の具体例】
・壁紙やフローリングの張り替え
・間取り変更
・浴室をユニットバスからセパレートタイプに変更
・システムキッチンに変更
・住宅性能を向上させる外壁塗装
【修繕費の具体例】
・借主が退去した後の原状回復
・畳の表替え
・定期的な外壁塗装
・付属設備の修理
原則として20万円以上の費用をかけてリノベーションを行った場合は、減価償却の対象とみなされるケースが多いです。
ただし、3年以内に定期的に行う修繕の場合は、20万円以上の金額でも修繕費として計上されます。
また、災害によって壊れた建物や家屋を修復する目的で行ったリノベーション費用は、修繕費として計上できます。
リノベーションを行った年に確定申告を行う
リノベーションにかかった費用を経費として計上するためには、確定申告を行う必要があります。
しかし、減価償却の場合、価値の減少に合わせて経費を計上するため、いつ申告をしたら良いか分からない方も多いでしょう。
結論、リノベーション費用を支払った年の確定申告で減価償却を行います。
確定申告を行わない場合、経費として認められず、納める税金が増えてしまうので注意してください。
また、減価償却としての費用を計上する手続きは国税庁のサイトから入力可能です。
税理士に相談する
減価償却費の計算は個人でも行えますが、計算を間違えたまま経費計上してしまうと申告が認められず、もう一度確定申告をしないといけない手間が発生したり、最悪の場合には追徴課税を請求されてしまう可能性があります。
そのため、減価償却による経費計上は会計や税の専門家である税理士に任せることをおすすめします。
税理士に相談することで、適切な会計処理と確定申告を行ってもらえるだけでなく、節税対策となるアドバイスをもらえるかもしれません。
国税庁が定める耐用年数の一覧

減価償却を計算するために耐用年数が必要ですが、それぞれ違う数値で計算してしまうと、国は適切な税金を回収できなくなります。
そのため、国が定めている耐用年数のことを「法定耐用年数」と言います。
国税庁が公表している法定耐用年数を一覧にまとめましたので、参考にしてください。
建物
| 構造・用途 | 耐用年数 |
| 木造・合成樹脂造のもの | 22年 |
| 木骨モルタル造のもの | 20年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 47年 |
| れんが造・石造・ブロック造のもの | 38年 |
| 金属造のもの | 4㎜を超えるもの:34年
3㎜を超え、4㎜以下のもの:27年 3㎜以下のもの:19年 |
建物附属設備
| 構造・用途 | 耐用年数 |
| アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの:15年
その他のもの:8年 |
| 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備:6年
その他のもの:15年 |
| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 15年 |
減価償却の計算方法

中古物件のリノベーションにかかった費用を減価償却する際の計算には以下の方法を用いることが一般的です。
・定額法
・定率法
ここでは、それぞれの計算方法について詳しく説明します。
定額法
建物の一部をリノベーションするのにかかる費用を減価償却する場合は「定額法」で計算します。
定額法の計算式は、「リノベーション費用×定額法の耐用年数に則った償却率」です。
例えば、鉄筋コンクリート造の建物を300万円かけてリノベーションした場合を例に計算してみます。
鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数は47年なので、償却率は0.022です。
つまり、1年間で減価償却として計上できる金額は300万円×0.022=6万6,000円となります。
定率法
定率法は毎年同じ額を減価償却するのではなく、年数の経過による価値の下落に合わせて減価償却する金額を決める計算方法です。
定率法の計算式は、「(リノベーション費用-償却累計額)×定率法の耐用年数に則った償却率」です。
キッチン設備の交換に100万円かかった場合を例に計算してみます。
キッチンの耐用年数は15年とされているため、償却費は0.133です。
つまり、1年間で減価償却として計上できるのは(100万円-0)×0.133=13万3,000円となります。
まとめ
賃貸オーナーが知っておくべき、減価償却や耐用年数などの用語の意味と減価償却の計算方法などについて解説しました。
リノベーション費用は大きく資本的支出と修繕費の2つに分けられ、資本的支出に該当する支出は減価償却によって経費計上します。
減価償却の計算を適切に行わないと、税金を多く納めなければならない可能性があり、賃貸経営にマイナスの影響が出てしまうでしょう。
賃貸物件を所有しているオーナーは、本記事の情報を参考にしていただき、複雑な減価償却費の計算を税理士に任せることをおすすめします。








