賃貸オーナーは知っておくべき!リノベーションの減価償却と耐用年数について徹底解説
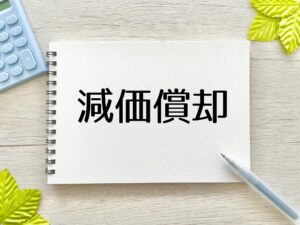
建物は築年数の経過とともに劣化していき、価値も減少します。
そして、価値の減少分を経費として計上する減価償却は、賃貸オーナーとして覚えておくべき重要な用語です。
また、減価償却と合わせて覚えておきたい用語が耐用年数です。
本記事では、リノベーションを考えている賃貸オーナーに向けて、減価償却や耐用年数などの用語の意味や減価償却の計算方法などを解説します。
賃貸経営の重要用語「減価償却」と「耐用年数」

まずは賃貸経営において重要な「減価償却」と「耐用年数」について、用語の意味を理解しておきましょう。
減価償却の仕組みとは?
一般的なビジネスにおける経費は発生した月に計上しますが、物件の取得のように資産に関わる経費は一括で計上するのではなく、価値の減少に合わせて年数をかけて経費計上を行います。
そして、この仕組みのことを減価償却と言います。
また、建物の劣化した箇所を修繕し、新たな価値を生み出すリノベーションにかかった費用も経費計上する際は減価償却で行わなければなりません。
高額な支出も全て経費として計上できるメリットがある一方で、減価償却費の計算を行わなければならないため、会計処理の手間が少しかかります。
減価償却の計算に必要な耐用年数とは?
前述したとおり、減価償却を行う場合には減価償却費の計算をしなければなりませんが、その計算に必要なのが耐用年数です。
耐用年数とは、減価償却する資産がどのくらいの期間で価値が無くなるかを指し示す指標です。
減価償却の対象となる資産には、耐用年数が法律で定められており、その年数に則って計算を行います。
また、素材や使用用途によって建物の法定耐用年数は異なり、建物に付属する設備にもそれぞれ耐用年数が定められています。
建物の減価償却で押さえておくべき5つのポイント

建物の減価償却で押さえておくべきポイントが5つあり、ここではそれぞれのポイントについて詳しく解説します。
建物の価値を高めるリノベーションは減価償却が必要
リノベーションにかかった費用が減価償却の対象となるか判断するには、資本的支出と修繕費のどちらに該当するかがポイントになります。
原則として20万円以上の費用をかけて行ったリノベーションは減価償却の対象とみなされるケースが多いです。
そして、3年以内に定期的に行う修繕の場合、20万円以上でも修繕費として計上されます。
また、災害によって壊れた建物や家屋を修復する目的で行ったリノベーション費用は修繕費として扱います。
資本的支出と修繕費の具体例
資本的支出と修繕費の違いは、リノベーションの施工内容で判断することも可能です。
具体的な施工例は以下のとおりです。
【資本的支出の具体例】
・壁紙やフローリングの張り替え
・間取り変更
・浴室をユニットバスからセパレートタイプに変更
・システムキッチンに変更
・住宅性能を向上させる外壁塗装
【修繕費の具体例】
・借主が退去した後の原状回復
・畳の表替え
・定期的な外壁塗装
・付属設備の修理
資本的支出と修繕費の定義は明確に決まっているわけではありません。
そのため、上記施工例はあくまで参考として考えてください。
どちらで経費計上するかはケースによる
資本的支出と修繕費の違いは明確に定義されていないため、どちらで経費計上するかは、会計的なメリットを考えると良いでしょう。
例えば、家賃収入が大きかった年は、修繕費としてまとめて計上することで翌年の税金を抑えられます。
一方で資本的支出で計上する場合は経費の金額を抑えられるため、利益が大きくなり、銀行からの融資を受ける際に有利になります。
賃貸経営戦略に合わせてどちらで経費計上するか選択しましょう。
リノベーションした年に確定申告する
リノベーションにかかった費用をその年の確定申告で減価償却します。
減価償却としての費用を計上する手続きは国税庁のサイトから入力可能です。
また、法定耐用年数をもとに減価償却費を算出するため、以下にまとめた建物の構造別の耐用年数を参考にしてください。
| 構造の種類 | 法定耐用年数 |
| 木造 | 33年 |
| 厚さ3mm以下の鉄骨造 | 28年 |
| 厚さ3~4mmの鉄筋造 | 40年 |
| 厚さ4mm以上の鉄筋造 | 51年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 70年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 70年 |
さらに、排水管などの建物設備の耐用年数は15年です。
税理士に相談する
減価償却による経費計上は複雑な税金の計算が必要な他、賃貸経営の継続にも大きく影響します。
そのため、税や会計の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相談するメリットとしては、税務や会計のサポートをしてもらえたり、確定申告を適切に行えたりするだけでなく、節税対策のアドバイスも期待できるでしょう。
減価償却の計算方法

リノベーション費用の減価償却を計算する方法としては、主に以下の3つがあります。
・定額法
・定率法
・簡便方
ここでは、それぞれの計算方法について詳しく解説します。
定額法
建物の一部をリノベーションするのにかかる費用を減価償却する場合は定額法で計算します。
例えば、外壁塗装や断熱工事、間仕切り壁の撤去・増設などの工事が該当します。
定額法の計算式は、「リノベーション費用×定額法の耐用年数に則った償却率」です。
鉄筋コンクリート造の建物を100万円かけてリノベーションした場合を例に計算してみます。
鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数は47年のため、償却率は0.022です。
つまり、1年間で減価償却として計上できるのは100万円×0.022=2万2,000円となります。
定率法
定率法は毎年同じ額を償却するのではなく、年数が経過するごとに償却費が減少する計算方法です。
トイレやキッチン、照明、エアコンの交換など、建物に付随する設備をリフォーム・リノベーションする場合には、この定率法がよく用いられます。
定率法の計算式は、「(リノベーション費用-償却累計額)×定率法の耐用年数に則った償却率」です。
トイレ設備の交換に100万円かかった場合を例に計算してみます。
トイレの耐用年数は15年とされているため、償却費は0.133です。
つまり、1年間で減価償却として計上できるのは(100万円-0)×0.133=13万3,000円となります。
簡便法
中古物件の購入と同時にリノベーションする場合は、再取得額に注意しましょう。
再取得額とは、既存の建物を現段階で同じように建てようとしたときにかかる費用です。
物件購入にかかった費用とは異なります。
また、リノベーションにかかった費用が中古物件の再取得額に対して50%を下回った場合は簡便法で減価償却費と計算できます。
簡便法の計算式は、「(中古物件の購入費用÷リノベーション費用)÷(中古物件の購入費用÷簡便法の耐用年数+リノベーション÷法定耐用年数)」です。
従来の算定式と簡便法のどちらが1回に多くの減価償却費を計上できるか比較した上で物件を選びましょう。
まとめ
今回は賃貸オーナーが知っておくべき、減価償却や耐用年数などの用語の意味や減価償却の計算方法などについて解説しました。
リノベーション費用は資本的支出と修繕費の2つに分けられ、資本的支出は一括で経費計上するのではなく、減価償却にて経費計上します。
適切に減価償却を行わないと余計に税金を納めなければならない可能性があり、賃貸経営に大きな影響が出てしまうので、本記事の情報を参考にしてください。
また、複雑な減価償却費の計算は税理士に相談することをおすすめします。








